授業で読んでいる本がおもしろい。ドミニカ系アメリカ人のJunot Diaz という人の書いたThe Brief Wondrous Life of Oscar Waoという作品である。まだ半分しか読んでいないのだが、なんとなく感想を書いてしまうのである。
主人公はタイトルにあるとおり、オスカーOscarという、ニュージャージーで暮らすドミニカ系の移民二世。デブでSFオタク、週末にはヤオハンで日本のオタクカルチャーにどっぷり浸かる。人生で最高にモテたのは7歳のころ、という、ちょっと哀れな男の子の生活が作品の主軸をなしているようなのだが…。
これがなんだか変な作品なのである。まずは大量に混入されるスペイン語。わたしはスペイン語を習ったことがないので全然わからない。ただし、なんとなく「ここはののしり言葉かな」とか「これはおじさんとかおばさんとか、とにかく親戚を表す単語だろう」ぐらいの推測はつくので、内容を完全に見失ったりはしないところがすごい。
また、この作品はいくつかの章にわかれているのだが、章によって話者が次々と変わり、人称も変わる。一章ではオスカーの悲惨な生活が三人称でおもしろおかしく(雰囲気は森見登美彦と似ているかもしれない)描かれるが、二章になると突然二人称の文がすこし挟まれ、直後にオスカーの姉ローラLolaの一人称の語りがおかれている。このローラの語りは母親とのかなりハードな確執が描かれていて、一章とはがらりと変わって切迫している。ちょっとThe Catcher in the Ryeのホールデンを思い出した。
半分読んだ段階で、この本のもつ一番の特異性は、実は「語り手」の存在にあるのだ、と気づいた。それは三章に現れる。全体的には三人称の語りによって、オスカーの母ベリシアBeliciaのドミニカでの十代からアメリカに移住するまでの経緯が描かれるのだが、なぜかところどころに「わたし」が乱入してくるのである。三人称の語りを他の人称と比較した場合、どちらかといえば中立的で俯瞰的な視点を読者に提供するもの、すなわち読者に出来事を伝達する、透明度の高いメディアといえるだろう。しかしここでは、たとえばベリシアが十代の頃働いていたレストランの客と話している場面で、語り手は「いまでも私は車に乗っているとときどきその男を見かける」などと、あまり関係のないような自分の体験をつい言ってしまう。それから、やたらに注が多い、というのもこの本の特徴なのだが、ここでも謎の「わたし」が自分の体験や感想、詳細なドミニカの歴史、そしてなぜか創作過程(「じつはここに出てきた○○という地名は草稿の段階では××にする予定だった」など)を明らかにしてしまったりする。こうした三人称の語りのなかでは違和感を与えるような一人称の発話が挿入されることによって、しだいに語りが抽象的な「視点」としてよりは、生身の身体をもった誰かの「声」として存在しているように思えてくるのだ。
語り手はいったい誰なのだろう、と思いながら読み進める。そうでなくても、どんどん先へ進みたくなる小説である。ついでにいうと、スペイン語だけでなく日本語もときどき出てくるのだ。アメリカの小説にkatana、kaijuなど、日本語がたくさん出てくるのはなんだか不思議だ。otakunessという言葉が出てきたときは笑ってしまった。
全部読んだら改めて書こうと思う。
2010/05/01
登録:
コメントの投稿 (Atom)
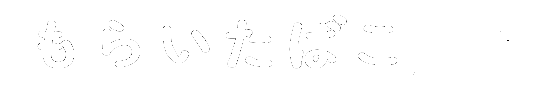




3 コメント on "The Brief Wondrous Life of Oscar Wao(前編)"
気になる小説だね。まとめて一段落とか引用して欲しいですm(_ _)m
その語り手、気になるなぁ。何物だ?
続きを待つ。
私も英語の授業で読んでいます。
コメントを投稿